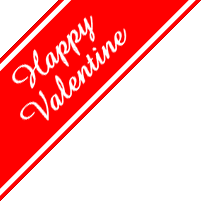
戦闘5/『父なる神』のおひざもとにて ゲーニッツ牧師
──いそがないと。
いそがないと、ねえさんが来ちゃう。
プラチナブロンドの細い髪が、2月の冴えた日差しに映える。時折強く吹きつける冷たい風にもひるむ事なく、少年は午後の街を走っていた。
目指す場所にたどりつき、呼吸を整えながら素早く計算する。途中の公園にあった時計で時間を確認したときから考えても、そう時間は経過していないはずだった。
大丈夫……イリュージョンを出る時間と、純粋な移動時間から考えれば、いくらねえさんでも全力疾走しつづけないかぎりまだついていないはず。買い物に手間取ったから、これから『ぼくが』必要とする時間を逆算するとぎりぎりだけど、そんなに時間はかからない!
すう、と深く息をすいこんで、彼は丁寧にニスを塗られた重厚な赤色のドアを押し開けた。
風の音がやむ。大きな窓からさしこむ陽光は、最盛期よりずっと控えめながら十分なぬくもりを投げ与えていた。
壇の上にいた人影が、物音に顔を上げて眼鏡をなおす。少年を見いだし、ゆるりと微笑んで、彼の人は目を落としていた聖書を閉じた。
「……ようこそ、おいでくださいましたね。どうなさいました、そんなに急いで?……お一人ですか」
「こんにちは、牧師様。ぼく一人です……今は」
背後でドアの閉まる音を確認し、ジャン少年は物怖じしない様子で歩をすすめた。
ここに来るときはいつも姉と二人でだった。そして、姉がこのおだやかに笑う青い目の牧師のことを好いているのも、彼はよく知っていた。
「姉も来ます。きっともうすぐです」
すいと顎を上げ、少年は壇の下から背の高い牧師をまっすぐに見上げた。牧師はおだやかに微笑ったまま無言でいた。少年が何か重要なことを告げるべく走ってきたことは、姉そっくりの白絹の肌が冷たい風の影響のみでなく紅潮していることと、早まっている呼吸から簡単に見て取れた。
「お願いです、牧師様。ぼくは姉に悲しい顔をさせたくありません……」
少年がさらに言葉をつなごうとした、まさにその瞬間だった。
ドアが軋むより早く、牧師が少年から視線をはずす。同様のタイミングで、しかし振り返るという動作ゆえに、ジャン少年がそれを見たのはこの背の高い男にほんの数瞬遅れをとった。
「こんにちは……」
極上の、笑顔。凍てつく蒼星を映した双眸が、このときばかりは春空に似たぬくもりを帯びる。
ねえさんの冬空色の瞳が、ぼくは好きだ。春色も、そりゃあ悪くはないけれど。
「こんにちは。ようこそ、ジャンヌ」
牧師が軽く腕を広げるようにして、彼女を招く。
牧師はキングのことをそう呼ばない。彼女も訂正を求めない。
『“キング”と名乗っておられるのだから、そうお呼びするのが筋かとは思います。確かに凛と響く良い名だと思いますが……。“ジャンヌ”、と。昔のように、そうお呼びしてよろしいですか?』
牧師はそう尋ね、姉はそれを断らなかった。ただそれだけだったが、姉がその名を呼ばせることを許しているのは世界にただの一人だけだった。
淡い嫉妬の思いは、神の名のもとに春の雪よりたやすく溶けて消える。
この男は聖職者であり、立派にその職を全うしている。その事実は、こと姉に関してはどこまででも苛烈になれるジャン少年から、ほぼ全面的な信用を引き出すに足りた。
「めずらしいですね、このような時間にいらっしゃるなんて。お仕事はもうよろしいんですか?」
「ええ、今日は早く出てきましたの。信用のおける子を残してきましたから、大丈夫です。……早かったのね、ジャン。学校からまっすぐ来たの?」
「うん。……ちょっと、牧師様に聞いていただきたいことがあったから……急いできたんだ」
そう言う少年の濃藍の瞳が、姉より牧師を視界に入れる。牧師は少年にかるく目配せしてみせた。
「ええ、つい先頃見えたばかりなんですが。まだお若いのに、きちんと懴悔することをご存じとは感心です。……良い弟君を持たれましたね」
にこやかにまた平然と牧師がごまかす。キングがジャンを褒められて、話についていかない訳がなかった。
「ありがとうございます、牧師様。でもほんとにいい子なんですの、牧師様にそうおっしゃっていただけると姉ばかでもないかと思えますわ」
白い女の美貌が、少女のようにほころぶ。その笑顔は、さながら一足早い春の到来を告げる女神のようだった。
ひだまりのおだやかさで牧師と笑みをかわしている春色の姉に、冬色の髪をはねあげて改めて話しかける。
「ねえさん、牧師様にお渡しするものがあるんでしょ?」
「えっ……いやだ、そんなこと言わないでよ」
少女のように頬を染める姉とじゃれあう弟の二人を、牧師は微笑ましく見ていた。割って入るほどのことはないと承知していた。
「牧師様、ねえさんがゆうべ『牧師様に』って作ったんですよ、お菓子作りなんて滅多にやらないねえさんですのに」
「いやだったら、ジャンってば!……あの、ずっとバレンタインのプレゼントなんて差し上げられませんでしたし……いろいろ考えたんですけど、マフラーも結局練習用のを編み上げるのがやっとで……」
弟に押しやられる形になって、キングは紙袋を抱いたままもじもじと牧師の前でうつむいた。
「私に?くださるんですか?……ありがとうございます、ジャンヌ」
バレンタインデーに手製のチョコレートを贈るという日本独特のイベントのことは知っていたが、自分の身に関係があるとは彼にも予想外だった。喜びを隠さずに笑ってみせると、キングは意を決した様子で胸に抱いた紙袋を差し出した。
「牧師様はチョコレートがお好きだと思って……。初めてでしたから……本を見たり、友人に聞いたりして作ったんですけれど、……受け取っていただけますか……?」
「もちろんですとも!覚えていてくださったんですか?毎日お忙しいでしょうに、手作りとは……わざわざ時間をさいてくださったのですね?ありがとう、嬉しいです……中を見てよろしいですか」
日頃、おだやかながら端然とした姿勢を強固に保ち続けている長身の男が、受け取った紙袋から両手のうちにすっぽり収まる大きさの箱を取り出して、この時ばかりは相好をくずした。箱と目の前の女の間を、青い視線が往復する。
パールブルーのリボンをかけられ、淡いブルーのセロハンで包まれた、白みの強い水色のプラスチック製ケースをとおして中身が見える。ココアパウダーをまぶしたトリュフは、サイズといい形といい少々ふぞろいではあったが、そのことがこの贈り物の価値を下げることなどありえなかった。
「美味しそうですねえ!早速、ひとついただきますね」
牧師の長い指が、器用にトリュフをつまみだす。笑って目礼し、口に入れて、ゲーニッツは期待と不安が微妙なバランスでブレンドされた表情でいる金色の女に今一度視線をやった。成層圏の青さの瞳が、キングを映して和む。
「……美味しいです。ありがとう、ジャンヌ」
牧師の感謝をこめた微笑をうけて、キングが笑う。安堵と歓喜に満ちた笑顔は、文字通り花がほころぶようなあでやかさだった。
「良かった……。牧師様に喜んでいただけて、嬉しいですわ」
「よかったねっ、やったかいあったじゃない、ねえさんっ」
弟の労いの言葉に頷く、少女のように可憐な表情にしばし目を奪われる。ふと我にかえって、ゲーニッツはかるく目を伏せかすかに吐息した。
春を纏った黄金の女と、冬を従える銀色の少年の両方に笑みを投げかける。
「さっそくアフタヌーンティーのお茶菓子にさせていただきます、それではお話はお茶を飲みながら男同士でうかがいましょうか」
「……はい!」
銀色の少年の濃藍の瞳が歓喜に染まる。キングはかるく首を傾げて笑い、牧師に会釈して告げた。
「じゃあ、私は失礼いたしますわ。やっぱり男の子ですものね」
「……ごめんね、ねえさん」
「いいのよ、ジャン。何でも話せる方がいるのはいいことだわ」
姉は弟の額にくちづけを残し、弟は姉の頬にくちづけた。
白い笑顔が丁寧な一礼を残して退堂するのを、それぞれ手など振って見送って、男二人はそれぞれの表情で吐息した。安堵と寂寥のまじったそれだったが、少年は前者を多くの割合で配合し、牧師は後者をやや目立たせていた。
「……さあ、ではすぐにお茶をご用意いたします。どうぞ、こちらの部屋へ」
「あ、はい、あの……これ、ぼくから牧師様に差し上げようと思って」
「……おや」
そう言って少年が鞄から取り出したのは、値札もついたままの真っ白な『粉砂糖』……パウダーシュガーであった。そっと差し出されたそれを受け取り、牧師は得心を得た様子で笑って頷いた。
「お心遣い、感謝いたします」
「いいえ、ぼくのほうこそお礼を申し上げます。ありがとうございます、牧師様……黙っていてくださって」
「なに。私としましても、なにも彼女をわざわざ悲しませるようなことはしたくありませんでしたしね、それは神も望まれますまい。……貴方も、彼女も、この優しいお心だけで、十分尊くていらっしゃいますよ」
少年の曰く、姉はチョコトリュフの製作過程で致命的ミスを犯したのだという。店の客には市販のものを渡すというふうに聞いていたが、肝心のトリュフが誰の手に渡る運命であるのか聞き出すのは結構骨の折れる作業であった、と彼は語り、牧師の濾れた紅茶にミルクと砂糖をたっぷり入れた。牧師も同様のことをし、さらにパウダーシュガーの封をきって頷いてやる。
白い小皿に移された、ココア色のトリュフにパウダーシュガーがかけられる。小山のような白い砂糖を、同系色の二対の瞳がしばし見つめる。最初に思い切った様子で動いたのは牧師であった。少年も意を決した様子でそれに倣う。
「……いただきます」
「お手伝いします、牧師様」
「ありがとう……」
言うまい言うまいと思えども、ぽそりとつぶやいてしまう。牧師の鉄壁の自制心はごくわずかながらひびわれを生じ、少年は素直に同情した。
「……塩入りのチョコレートというのがこんなにすごいものだとは、存じませんでした」
「間違えて塩入れたココアって、ものすごく不味いんですよね……。試さない方がいいですよ」
「そうします」
無言になりがちな二人を責められる者はなかっただろう。二人は黙々と証拠隠滅をはかり、ついに成功をおさめたのだった。
その間、消費された紅茶はポットに1本どころではきかなかったという。
──ゲーニッツ牧師、戦利品(手作りチョコレート)入手すれども破壊力大。愛はすべてに優先したらしい。