女神の揺籃
アナザーエンディング
『女神の揺籃』、こんなふうに穏やかには絶対終わらないと思いますが。
あくまで、『アナザーエンディング』ということで。
血も家も棄ててしまえること。それは強さなのか、それともただの逃げなのか。
ぼくにはわかりませんけれども。
どこまでも青い海の色。
のみこまれる思い。
血の宿命も、運命も、すべてのみこんで。
きっといつまでも、ただ静かに。
もしかしたら幸せなのかもしれない日々をおくってください。
イメージとしては、ギリシアはサントリーニ島。
エーゲ海の青と砂浜の白を思って書きました。
このおはなしで使用した素材はすべてdpi Web Graphixさまの作品です。
ありがとうございました。
この土地に、新しい住人がやってきたのはそう古いことではなかった。
まだ若い男女の二人連れは、どちらもなかなかの美貌であった。よそ者である彼らを快く思わない者たちであっても、それは認めざるを得なかった。
豪奢な金の髪と蒼氷色の瞳の女は、その美貌と話術ですぐに若い女たちの中に溶け込んだ。髪を真っ赤に染めた鋭い瞳の男は、人の多く集まる場所では居心地が悪そうにしていたが、連れの女の言うことを聞いておとなしくしているようだった。
『夫婦』という訳ではなさそうだった。『姉弟』という訳でもなさそうだった。それでも女は無愛想な男をよくかばっていたし、男もそうする女をよく気遣っていた。まるで、比翼の鳥のように。
丘の上の白い石作りの住居に住まい、ささやかに暮らしはじめたその二人に注がれる好奇の視線はやがて落ち着き、土地の者たちは普段どおりの生活に戻った。
丘の上の家からは、時折澄んだ歌声が風に乗って聞こえてきた。歌詞は彼らの知らない言語だったが、やわらかで物悲しいメロディはいつかこの土地になじんでいた。
波の音が、聞こえる。洗いざらしの真っ白いワイシャツの肌触りも気持ち良く、テラスに出した長椅子の上に寝転んで、読みさしの薄い小説本など顔に乗せたままうたた寝をしていた男は、伏せた瞼の上から強い日差しを感じて顔をしかめた。
「……こおら!起きなさい」
顔に乗せていた小説片手に、白いサマードレスを纏った女が見下ろしてくる。腕で日差しを遮りながら、眠そうに言い返す。
「……なんだ……おまえか。いいじゃないか、寝かせろよ」
「ひなたぼっこするのに来客用のソファを使うなって言ってるの!ちゃんと買ったのがあるでしょうに」
すんなりとした白い指が、びし、とテラスの隅に出してあるデッキチェアを指さす。男は不満げに上体を起こした。
「あれは寝心地が悪いから嫌いだ。こっちのほうがいい」
「……高かったのに、このソファ……あっというまにこんなに日に焼けちゃって……」
額に手をやって嘆く女に、男は無邪気に言ってのけた。
「もうひとつ買えばいい。違うか?」
年若い彼のあまりの無邪気ぶりに、首を振り振り眉をひそめる女の様子に、男は口元に手をやってうつむく。しょぼん、という文字がその背後で踊っていた。
「駄目か……?」
しょげかえっているのが見て取れる。もし彼が犬だったら、耳をぱたりとねかせてきゅーん、と鳴いたかもしれない。
「……しょうがないな。わかった、客用のはもうひとつ買おうか。……選びに行かないとね。車出してくれる?」
「今からか?」
そう言ってみるが、既にそのつもりの女に差し出された手を素直に取って立ち上がる。男はひとつ伸びをした。
「……今日も、いい天気だな」
なんでもないようなことを、なんでもなく言う。それさえ、少し前ならこの男の口から出ることはまずなかった。こうして暮らすようになった今となっては、ごく普通に起こるようになったのだけれど。
女は笑って、男の長い前髪に指をからめた。乱れた一房を整えてやる。
「そうだね。今日も、とてもいい天気」
女の白い手首を、大きな手で無造作にとらえる。小さく首をかしげた女の反応など気に止めず、きれいに整えられた爪の先にそっと唇を触れさせる。
そのまま女の手を己が頬にあてがって、その存在を実感しながら彼は表情を和ませた。
「ほんとうに、いい天気だな……」
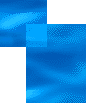
俺を、閉じ込めてくれないか。
俺が、どこかへいかないように。
そう言われたときは何事かと思ったが、彼の様子を見ていて、その言葉はレトリックなどではなかったことがよくわかった。
本心から、彼はそう言ったのだ。
『暴走』と呼ばれた、彼の血が彼の肉体に引き起こす悪意に満ちた現象。一族の怨念に精神を、人外の力に肉体を支配され、破壊と殺戮を繰り広げて彼は哭いていた。
俺は怖い。俺が俺ではない何かになってしまいそうな気がして怖い。
……だから、助けて。俺をどこかに閉じ込めてくれ。俺を狂わせるあの姿を見なくてすむ場所まで、つれていってくれ。
血まみれになって震えていた彼にそう言われたとき、彼女には断ることはできなかった。
「わかった……つれていくよ。どこまででも」
そう告げたときの、暗闇の中にようやくひとつの光を見いだしたかのような表情に、彼女はすべてを振り捨てることを決断したのだった。
乾いた空気と、空と海に抱かれる静かな暮らしは、男の精神から無闇な緊張と攻撃性を徐々にそいでいった。男は次第に和らいだ笑顔を見せるようになり、口にする言葉も穏やかなものになっていった。
それは、彼女にとっては確実に喜ばしいことだった。
「星が綺麗!おいで、日本じゃこんな空見えないでしょう」
「ああ……俺の家のほうでは見えないな、本当に……宝石箱をひっくりかえしたような空だ」
ある晩、食事を終えた女は、テラスに出ると男を招いた。しばし、夜風を楽しみながら空をながめる。
ほんとうに星が降ってきそうな空をまぶしそうに見上げていた男は、やがて視線を己が手に落としてつぶやいた。
「俺はもう……炎は出せないかもしれないな」
「えっ?」
一瞬、何を言われたのかわからない様子で女が聞き返す。男は口元に淡く笑みをはいた。
「……心残りはない。あんな力に未練はないさ、ない方がいいくらいだ。炎は出せなくても、おまえと俺自身を守ることができれば十分だ」
ためらいなく、男は言い切った。視線を金の女に転じて、以前とは異なるしなやかな勁さを感じさせる表情で厳かに頷く。
「俺の力は、俺が墓まで持っていく。八神の血は俺で絶える。そのほうがいいんだ」
「それで……いいの?」
彼女は男の宿命を知っていたが、それにかかわることは不可能だった。
己の中にある呪わしい血を、その身の裡に飲み込んだまま時の流れに埋没させることを選ぼうとしている男に、せめてそっと問いかける。彼は穏やかに、しかしはっきりとその問いに頷いた。
「俺がそう決めた。『宿命』とやらを捨てることに対する悔いはないし、一族の因縁も知ったことではない。……『宿命』とやらに本当に力があるなら、奴らのほうが俺を見つけ出すだろうよ。だが、俺はもうそんなものに興味はない」
淡々と言葉を綴ってから、彼は今一度視線を落とした。申し訳なさそうに、謝する言葉を紡ぎ出す。
「すまないな。おまえは俺の子供が欲しいと言ってくれたのに」
女は無言で首を振った。その表情は、どこか嬉しそうでさえあった。
「子供が欲しくなったら、養子をもらいましょう。血がつながってなくても、家族にはなれるわ」
やさしくひびく声に頷く代わりに、微笑む女をそっと抱きよせて男は目を閉じた。相手の温もりと息遣いを感じながら、金の髪を梳く。
「……俺とおまえの子なら、見てみたい気もするがな……」
照れたように、そっと言ってみる。女は涼しげに笑った。
「どっちに似ても、大変そうね」
「そうだな……」
彼女の白い額に軽くくちづけて、もう一度抱きしめる。
「おまえが……俺を守ってくれた。今度は俺の番だ。おまえを傷つける奴がいたら許さない。どこに逃げても捜し出して、楽になど死なせない」
おまえの心も、身体も。
傷つける者がいたならば、必ず後悔させてやる。
耳元でささやかれる低声の台詞は物騒な響きを有していたが、どれほど多くの愛の言葉もこれにはかなわないように思われた。
本当に相手を殺しに行くかどうかなどは、この際問題ではない。それほどに大切だと言いきる、思いの強さと優しさがいとおしい。
肩口にうめていた白い頬を離し、男を見上げてさやかに微笑う淡いブルーの瞳が揺らめいた。睫毛が震えて、涙がこぼれおちる。
「何で泣く?何か言ってはいけないことを言ったか?……どうして泣く」
おろおろと涙を拭っては心配そうな顔をする男に、女は小さく首を振って笑顔を向けた。
「嬉しいの。嬉しいのよ」
幾重にも重なっていた冷酷と無関心と自棄、そして狂おしいほどの執着。それらで頑なに自らを縛り付けていた彼は、それらの重い足枷をはずした時こんなに優しくなれるのだ。
目尻に浮かぶ涙に唇を寄せてそれをなめとる。そっと涙を吸って、もう一度女の細い肩を抱きしめて、男は低くささやいた。閨の睦言さえかなわぬほどの甘やかさであった。
「一緒に暮らそう。ずっと一緒に生きていこう」
置いてきた何かを恋しんで泣く暇などないくらい、傍らにないものたちのぶんまで俺がおまえを愛するから。
微かに震えている腕が、そう語っていた。
月さえも眠る、静かな夜だった。
Author's Note
アップは1998.3.25です。
八神庵お誕生日おめでとう、ということで。せめて「ある意味では確実に」幸せなのではないかという話にしてみました。
「宿命なんて知らない」。「力なんていらない」。本来なら、庵は絶対口にしない言葉ですものね。
日本全国津々浦々の庵ファンの皆様。僕も庵を愛してます。これが僕の彼への愛です。
過去の情報全部抹消して、家のまわりと島全体に何重にも結界張って(うちのキング『魔女』ですし、庵なら結界のひとつやふたつ張れるでしょう)、徹底的に逃げて隠れて。ちっちゃい日本食の店でもやってるんじゃないかな?守護霊にゲーニッツやら庵ママやら妹やらなんぼでも憑いて(汗)そうですし、ジャン君はキングさえ幸せならすべて見て見ぬふりができますから。
この時点の生身の人間で彼らの居場所を探し出せるのは……いなくはないでしょうが(ロバートとかハゲとか)。ろばやんは説得できず、リョウに彼女らの居場所を隠し通すしかないでしょうし、ハゲは……「お前がそうすることを選んだんだな?」「なら、何も言わねえ。誰にも邪魔はさせねえよ。弟君の事も心配すんな……」「ただ、もし何か起きたら……必ず俺に言え。いいな、それだけは約束だ」と言ってくれるのでは。
ちづるは結界にハネられて駄目でしょう。「その島の存在は知っていてもそこを探す気になれない」というふうに結界が意識の方向を逸らしてしまうでしょうから、結果的に発見できないということになります。京は……きっと「わかって」しまうから探そうともしないでしょうね。庵がどうして姿を消したか、わかってしまうから。京も「宿命なんか知ったこっちゃねえ」のクチですからね。